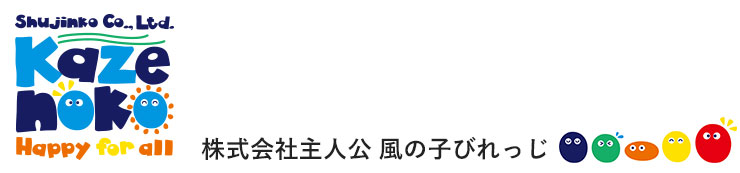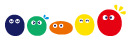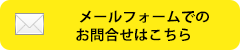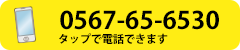理念・ビジョン
私たちの想い
仕事に厳しく、自分に優しく、人にはもっと優しく
私たちのビジョン(10年後)
~自創自走する職場の実現~
仕事が面白いと感じ、職場が楽しいと感じ、何より人に喜んでいただくことに最高の喜びを感じている。
自分の人生を自らが主役だとの気概を持って、より良くなり続ける様に変化していく。
私たちのミッション(使命)
安全性(事故防止)と権利擁護(虐待防止)を土台にして、メンバー様個々のニーズに合わせた「発達支援」「生活支援」「就労支援」を実践すること。
メンバー様の発達段階に合わせた個々の能力内自立をサポートをしていくこと。
株式会社主人公 経営理念
「Happy for all」
全ての人たちをハッピーにするのではなく、全ての人たちと共にハッピーになる。
幸福感は人によって感じ方も違い、他人から押し付けられるものでもありません。
また、幸福感の持続性も人によってまちまちですし、すべての人の感じ方は変化していくものです。
それらを踏まえて尚、一緒にハッピーになるという理念は、航海の羅針盤とする価値がある事だと考えます。
株式会社主人公 倫理綱領
前文
当法人では、「Happy for all」の理念のもとに、心身に障害のあるメンバーが、人間としての尊厳が守られ、豊かな人生を自己実現できるように支援することが、私たち風の子職員の責務です。そのため、私たち風の子職員は支援者のひとりとして、確固たる倫理観を持って、その専門的役割を自覚し、自らの使命を果たさなければなりません。
ここに職員倫理綱領を定め、私たち風の子職員の規範とします。
1.生命の尊厳
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバー一人ひとりをかけがえのない存在として大切にします。
2.個人の尊厳
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーの、ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。
3.人権の擁護
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーに対する、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。
4.社会への参加
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーが、年齢、障害の状態などにかかわりなく、社会を構成する一員としての市民生活が送れるよう支援します。
5.専門的な支援
私たち風の子職員は、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、心身に障害のあるメンバー一人ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援し続けます。
6. 理念と精神
私たち風の子職員は、私たちに関わる全ての人の「Happy for all」を叶えていく為に「Changes for the Better 」の精神で支援を行ってまいります。
株式会社主人公 風の子職員行動規範
前 文
私たちは、誰もがかけがえのない人生をより豊かに生きたいと思っています。そして個人の尊厳と平等が大切にされる社会の実現を願っています。
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーの人格及び尊厳を尊重して接することを基本とし、支援者としての役割を果たします。そして、メンバー一人ひとりを、かけがえのない存在として大切にします。
私たち風の子職員は、メンバーの自己実現と成⾧を目指し、自立のための支援を専門的に行います。
私たち風の子職員は、メンバーの「生命の尊厳、個人の尊厳、人権の擁護、社会への参加」を基本として、メンバーの社会参加に向けての取り組みを積極的に推進し、「Happy for all」の理念のもと、メンバー一人ひとりの笑顔が輝く、より豊かな社会を創り上げていくために、この「風の子職員行動規範」を遵守し、行動するための規範とします。
基本的姿勢
(1)私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーの人間としての尊厳を大切にして、メンバーの権利擁護に努めます。
(2)私たち風の子職員は、支援者の立場を自覚し、メンバーの主体性、個性を重んじます。
(3)私たち風の子職員は、メンバーが快適で豊かな生活が出来るように支援します。
(4)私たち風の子職員は、福祉施設としての役割と専門性を認識し、保護者をはじめ関係機関や地域住民、ボランティアと協働して、地域に貢献できる施設づくりに努めます。
(5)私たち風の子職員は、支援者としての専門性を高めるため、絶えず研鑽に努めます。
具体的行動規範
<人権の尊重>
① メンバーに対して、いかなる理由があっても、体罰は一切しません。
② メンバーに対して、からかい、軽蔑、嘲笑などの差別的な態度はとりません。
③ メンバーの人権を尊重し、呼称は年齢に応じて適切なものを使用していきます。
④ メンバーへの支援にあたって、プライバシーの保護に配慮します(個人情報保護の徹底)
<利用者の主体性の尊重>
① 支援者としてメンバーが安心感をもてるような態度で接します。(命令的や否定的な言葉を慎み、むやみに大声で注意したり呼びつけたりしません。)
② メンバーの個々の性格や生活のペースを尊重し、一方的な理由で行動を強要しません。
③ メンバーの⾧所やがんばりなどを積極的に認め、自立していこうとする力を支援します。
④ メンバーが楽しい雰囲気の中で生活できるよう工夫して取り組みます。
<一人ひとりのメンバーにふさわしい支援>
① メンバー一人ひとりの障害特性や能力、個人の状況やニーズを的確に捉え、個別支援計画を作成(日中一時支援は除く)して、メンバーの了解のもとに、自立・自己実現に向けた支援を行います。
② メンバー個々について適切なコミュニケーション手段を工夫するなどして意思の疎通を図ります。
③ メンバーの健康管理、安全確保、体力に配慮した支援に努めます。
④ メンバーが不安定な時や興奮した状態にある時、感情的にならず、行動の背景などの理解に努め、冷静に対応します。
⑤ メンバーの自傷、他害等の危険回避のための行動上の制限については、本人・家族への明確な説明を行います。
<メンバーの社会参加支援>
① メンバーの社会参加の機会が最大限に保障されるよう努め、また社会参加を妨げる障壁に対しては、その障壁を取り除くための積極的な働きかけ、解消に努めます。
② 様々な活動や社会参加の機会を提供し、メンバーの意思決定を支援していきます。
③ メンバーが公共施設、飲食店やマーケット等地域の社会資源を利用する機会を持てるように支援するとともに、地域行事に参加するなど、社会参加の機会を広げるように支援します。
<メンバー、保護者に対する情報の提供>
① メンバーとの利用契約に際しては、事前に見学や面接、体験利用を行い、施設支援の基本方針などを、十分に説明します。
② 施設の事業計画や支援の状況に関する情報は、お便りやホームページ・インスタグラム等で定期的に報告・説明して、保護者・家族の協力を得るように努めます。
③ 日々の活動や作業を通じて得たメンバーの情報は、職員同士で十分に共有し、できる限り正確に保護者や家族にお伝えできる様努めます。
<開かれた施設づくり>
① 風の子職員と保護者はお互いに協力し合い、情報を提供することで共に学び合いながら連携し、より良い支援を目指します。また、保護者と共に学び合い成⾧し会える場としての施設作りに努めます。
② 専門機関としての役割を認識し、家族支援をはじめ地域のニーズに応えられる利用しやすい施設づくりに努めます。
<支援専門職の自覚>
① メンバーへの支援の専門職としての誇りと自覚を持ち、支援技術向上のために、積極的に研修会などに参加するなどして自己研鑽を重ね、資質の向上に努めます。
② 風の子職員としての誇りと自覚を持ち、組織の一員として、チームワークを重んじたメンバー支援を行います。
③ この行動規範をより実践的な規範とするために、たえず自己点検、相互点検を怠らず、必要に応じて、各会議においてその実践状況を相互に確認するものとします。
付則 この風の子職員行動規範は、毎年度全職員により確認をし、必要があれば見直しを行います。
株式会社主人公 虐待防止・身体拘束適正化のための指針
付則 この虐待防止・身体拘束適正化のための指針は、毎年度全職員により確認をし、必要があれば見直しを行います。